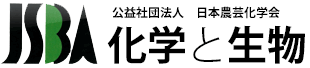Page. 294 - 301
(published date : 2013年5月1日)
栄養応答シグナルは,アミノ酸やグルコースなどの栄養素摂取や活動により刻々と変化する細胞内のエネルギー状態を認識し,個体のエネルギー・栄養代謝の恒常性を維持している.栄養過剰状態では,栄養応答シグナルの調節不全として,mTOR経路(栄養過剰シグナル)増強やSIRT1, AMPK(エネルギー不足感受シグナル)の減弱が生じることで,エネルギー代謝の恒常性が正の方向へ破綻する.その結果,肥満・メタボリックシンドローム・糖尿病を引き起こしている可能性が考えられるため,栄養応答シグナル調節不全の是正,すなわちmTOR経路抑制やSIRT1, AMPK活性化が治療標的として期待できる.