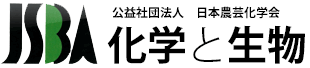Page. 512 - 518
(published date : 2014年8月1日 advanced publication : 2014年7月20日)
菌類は古くから発酵食品製造に用いられてきた.わが国はこの分野に強みをもっており,独自の文化ともなっている.和食(日本人の伝統的な食文化)が先頃ユネスコ無形文化遺産に登録されたのもその表れと言えよう.近代発酵産業でも菌類は重要な役割を果たしており,20世紀後半にはいわゆるブロックバスター医薬が菌類から発見された.最近,発酵食品や天然物創薬に利用されてきた菌株について分子系統学的手法により新しい分類学や命名のメスが入れられ,興味深い事実がわかりつつあるが,これは貴重な歴史的菌株そのものが保存されていたからにほかならない.われわれはニッチとしての天然物創薬を夢見て,10年以上にわたり北海道から西表島まで幅広く,自然界でほかの生物と何らかのインタラクションのある菌類に特化して探索を続け,15,000以上の菌類菌株ライブラリと40,000以上の培養抽出物ライブラリを構築した.抽出物ライブラリはさまざまな生物活性データを付加してデータベース化しその利用を図ってきた.ここではそのコンセプトと最近の話題を紹介したい.