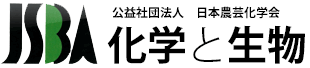セミナー室
/ これからのバイオイメージング技術
化学発光を利用した生理機能の可視化
Vol.49 No.8 Page. 555 - 559 (published date : 2011年8月1日)
齊藤 健太1,
永井 健治1,2
- 北海道大学電子科学研究所
- JSTさきがけ
概要原稿
近年の蛍光ライブイメージング技術の著しい発展により,細胞,組織,個体を生きたまま可視化し生命現象を時空間的に理解することが可能となった.しかし,蛍光ライブイメージングが一般的になり観察対象が魚,トリ,マウスといった生物個体に広がる一方で,蛍光観察が有するサンプルへの光毒性や自家蛍光といった問題が顕著になりつつある.その中でホタルに代表される化学発光を用いたライブイメージングにも注目が集まりつつある.化学発光は蛍光と違い外部からの励起光を必要としない.そのため自家蛍光や生物個体に対する光毒性といった問題とは無縁である.このように蛍光に比べて利点のある化学発光であるが,放出するフォトン数が少ないため画像化には長時間の露光(数秒~分のオーダー)を要する.また励起光は必要としないもののルシフェリンなどの発光基質を細胞や組織に導入する必要があるため,動きの速い現象や発光基質を取り込みにくい細胞などの観察には不向きであり蛍光観察ほどには普及していない.ところが最近になって,より明るい化学発光タンパク質が報告されはじめ,またEM-CCDカメラに代表される超高感度CCDカメラの普及もあいまって化学発光でも実時間でイメージングできる時代が到来しつつある.今回は,化学発光を利用したライブイメージングについて筆者らの開発したセンサーを中心に紹介する.
リファレンス
- 1) O. Shimomura : “Bioluminescence”, World Scientific, Singapore, 2006.
- 2) 永井健治:蛋白質 核酸 酵素,51, 1989 (2006).
- 3) J. R. James, M. I. Oliveria, A. M. Carmo, A. Iaboni & S. J. Davis : Nature Methods, 3, 1001 (2006).
- 4) L. I. Jiang et al. : J. Biol. Chem., 282, 10576 (2007).
- 5) K. Saito, N. Hatsugai, K. Horikawa, K. Kobayashi, T. Matsuura, K. Mikoshiba & T. Nagai : PLoS ONE, 5, e9935 (2010).
- 6) A. M. Loening, T. D. Fenn, A. M. Wu & S. S. Gambhir : Protein Eng. Des. Sel., 19, 391 (2006).
- 7) T. Nagai, S. Yamada, T. Tominaga, M. Ichikawa & A. Miyawaki : Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 101, 10554 (2004).
- 8) J. Nakai, M. Ohkura & K. Imoto : Nature Biotechnol., 19, 137 (2001).
- 9) H. Hoshino, Y. Nakajima & Y. Ohmiya : Nature Methods, 4, 637 (2007).
- 10) D. M. Close, S. S. Patterson, S. Ripp, S. J. Baek, J. Sanseverino & G. S. Sayler : PLoS ONE, 5, e12441 (2010).

本文はトップページからログインをして頂くと表示されます。