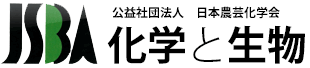「化学と生物」文書館
日本の澱粉科学と産業の発達史を辿って
I. 澱粉の科学―古典から近代まで
Vol.50 No.3 Page. 203 - 208 (published date : 2012年3月1日)
概要原稿
澱粉は食料の中で非常に重要なカロリー源として用いられてきたため,古い時代から研究の対象とされてきた.食品,製紙や繊維の糊料として必要な種々の物性や利用に関する研究は行なわれていたが,化学的な面で著しい進歩が見られたのは1940年の前後数年の間である.本稿の御依頼は「澱粉の科学 ― 異性化糖の開発」であったが,異性化糖の研究が開始される背景となった日本の澱粉科学および澱粉関連産業の過去50年の研究の流れと,その中で筆者自身の歩んだ道を関連させながら述べさせていただくことにした.
リファレンス
- 1) Robert P. Walton : “A Comprehensive Survey of Starch Chemistry”, The Chemical Catalog Co., Inc., 1928, Vo. I (pp. 240), Vol. II (pp. 360).
- 2) 二国二郎:“デンプンハンドブック”,二国二郎(編),朝倉書店,1961, p. 20.
- 3) K. H. Meyer & P. Bernfeld : Helv. Chim. Acta, 23, 875 (1940).
- 4) T. J. Schoch : J. Am. Chem. Soc., 64, 2957 (1942).
- 5) K. Freudenberg : Ann. Rev. Biochem., 8, 81 (1939).
- 6) D. French & R. E. Rundle : J. Am. Chem. Soc., 64, 1651 (1942).
- 7) R. E. Rundle & D. French : J. Am. Chem. Soc., 65, 1707 (1943).
- 8) 二国二郎(編):“澱粉化学”,朝倉書店,1951, p. 540.
- 9) 二国二郎(編):“デンプンハンドブック”,朝倉書店,1961, p. 731.
- 10) 二国二郎(監修),中村道徳,鈴木繁男(編):“澱粉科学ハンドブック”,朝倉書店,1977, p. 632.
- 11) 不破英次,小巻利章,檜作 進,貝沼圭二(編):“澱粉科学の事典”,朝倉書店,2003, p. 554.
- 12) 山本和貴,松木順子,貝沼圭二(編):“澱粉の科学と技術―澱粉研究懇談会50年の歩みと展望”,澱粉研究懇談会出版,佐藤印刷所,水戸,2010, p. 232.
- 13) 二国二郎:調理科学,2, 6 (1969).
- 14) K. Kainuma & D. French : Biopolymers, 11, 2241 (1972).
- 15) 貝沼圭二:調理科学,13, 83 (1980).
- 16) Y. Ikawa, D. G. Glover, Y. Sugimoto & E. Fuwa : Starch/Stärke, 33, 9 (1981).
- 17) S. Hizukuri : Carbohydr. Res., 147, 342 (1986).
- 18) I. Hanashiro & Y. Takeda : Carbohydr. Res., 306, 421 (1998).
- 19) 貝沼圭二:日本農業研究所報告「農業研究」,第15号,1 (2002).
- 20) 鈴木繁男:澱粉科学,27, 211 (1980).
- 21) 山中 啓:化学と生物,48, 643 (2010).
- 22) 岡田厳太郎:応用糖質科学,1, 4 (2011).
- 23) 二国二郎:澱粉工業学会誌,4, 38 (1956).

本文はトップページからログインをして頂くと表示されます。