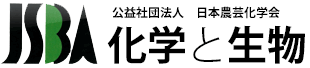随想
日本のビタミン研究の流れ
Vol.50 No.9 Page. 684 - 687 (published date : 2012年9月1日)
概要原稿
稲が中国の長江流域から渡来したのは,縄文時代末期(紀元前5世紀)といわれています.当初は玄米を食べていたのが,しだいに白米を賞味するようになり,江戸期も元禄時代(17~18世紀)になると,都市では白米中心の食生活が一般化しました.それとともに脚気(後年,ビタミンB1欠乏症と判明)が広がりました.脚気患者が田舎に移り住み,玄米食を食べると治るので,江戸患い,都患いなどと呼ばれていました.ヨーロッパでは,古くから遠洋航海において,壊血病(ビタミンC欠乏症)が知られ,15世紀末からの大航海時代には深刻な問題でした.そのうち経験的にミカン類が壊血病を防ぐことが知られ,18世紀,英国海軍ではレモン,オレンジを計画的に摂取するようになりました.
リファレンス
- 1) 松田 誠:“高木兼寛の医学”,東京慈恵会医科大学,2007.
- 2) 清水祥一:ビタミン,82, 579 (2003).
- 3) 社団法人鈴木梅太郎博士顕彰会,鈴木梅太郎先生刊行会:“鈴木梅太郎先生伝”,朝倉書店, 1967.
- 4) M. Fujiwara, H. Watanabe & K. Matsui : J. Biochem., 41, 29 (1954).
- 5) 須田立雄,尾形悦郎,小椋陽介,西井易穂:“ビタミンD―その新しい流れ”,講演社サイエンティフィック,1982.
- 6) S. A. Salisbury, H. S. Forrest, W. B. Cruse & O. Kennard : Nature, 280, 843 (1979).
- 7) J. Westerling, J. Frank & J. A. Duine : Biochem. Biophys. Res. Commun., 87, 719 (1979).
- 8) K. Matsushita, H. Toyama & O. Adachi : “Advances in Microbial Physiology,” Vol. 36, ed. By A. H. Rose & D. W. Tempest, Academic Press, London, 1994, p. 247.
- 9) 岡島俊英,中井忠志,谷澤克行:生化学,83, 691 (2011).
- 10) 虎谷哲夫:生化学,83, 591 (2011).
- 11) H. Hayashi, H. Mizuguchi & H. Kagamiyama : Biochemistry, 37, 15076 (1998).

本文はトップページからログインをして頂くと表示されます。