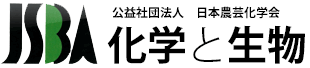Page. 7 - 9
(published date : 2013年1月1日)
被子植物の花の多くは,雄ずいと雌ずいをともにもつ両性花であるため,自己の花粉が雌ずいにつきやすい構造となっている.実際,イネやシロイヌナズナなど自己の花粉と受精して種子を残す自殖性の植物も存在するが,多くの植物種は自己と非自己の花粉を識別し,自殖を回避する自家不和合性と呼ばれる仕組みを発達させてきている.これは,自殖により引き起こされる悪い影響(近交弱勢)を回避しうる,種の遺伝的多様性を維持し有益な遺伝子を集団内に素早く浸透させうる,といった自家不和合性のもつ利点が進化上有利に働いたためと考えられている.自家不和合性は,一般に一つの遺伝子座(S遺伝子座)によって調節されており,ここには構造多型性を示す少なくとも2つの因子(雌ずい因子と花粉因子)がコードされている.雌ずい/花粉因子をコードする複対立遺伝子のセットは,組み換わることなく単一の遺伝子ユニットとして遺伝するため,Sハプロタイプ (S1, S2, …, Sn) と呼ばれており,その数 (n) はアブラナ科やナス科の自家不和合性種では50種類以上に及ぶことが知られている.そして,同じ個体の花の間ではもちろん,別の個体であっても花粉と雌ずいが同一のSハプロタイプをもつ場合に受精が抑制される.この現象のメカニズムの説明として,同一Sハプロタイプに由来する「自己」の雌ずい因子と花粉因子が「鍵と鍵穴」の関係で相互作用する場合に不和合反応が誘導されるという「自己認識」モデルが予測された(1, 2).