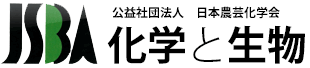Page. 500 - 506
(published date : 2013年7月1日)
現在,地球上にはおよそ160万種の生物が生息するとされている.昆虫はその60~70%を占め,80~100万種が記載されているが,未記載のものも含めると,1,000万種をゆうに超えるのではないかと言われている.一方,日本で記載されている昆虫は約3万種である.そのような昆虫のうち,「人間生活に害や不快感を与える小動物の総称」として“害虫”が存在する.全世界の害虫の種数は8,000~10,000種(昆虫全体の1%以下)と推定され,私たちの国では約2,600種の昆虫が農林業害虫としてリストアップされている.また,外国から侵入し,新しい土地に住み着いた昆虫を帰化昆虫と呼ぶが,それらが害虫だった場合は“侵入害虫”となる.日本において侵入害虫が問題となってきたのは,明治維新以降である.開国して,江戸時代の鎖国政策から開放政策に転じ,諸外国と人・物資の交流が盛んに行われた結果,人や農作物,苗木に付着して侵入害虫がやってきた.