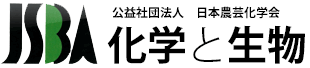Page. 77 - 79
(published date : 2012年2月1日)
カフェオイルキナ酸 (caffeoylquinic acid, CQA) は,コーヒー豆から初めて単離された成分である.コーヒー豆の他に,サツマイモ,プロポリス,野菜などに多く含まれていることが知られている.コーヒー酸のカルボキシル基がキナ酸のヒドロキシル基とエステル結合した構造をもつ化合物であるCQAには,カフェオイル基の数や位置に応じて,5-CQA(クロロゲン酸),3,4-di-CQA, 3,5-di-CQA, 4,5-di-CQA, 3,4,5-tri-CQAなどのCQA類縁体が存在する.その生理活性作用としては,抗酸化,抗腫瘍,抗高血糖,抗炎症などが挙げられる.本稿では,筆者らが見いだしたCQAの新しい生理活性作用,神経細胞保護作用や老化促進モデルマウス (senescence-accelerated prone 8 mouse;SAM-P8) の学習・記憶障害の改善効果について紹介する.