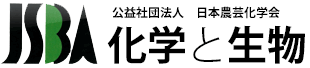Page. 189 - 192
(published date : 2014年3月1日)
ハダカデバネズミ (naked mole-rat, Heterocephalus glaber, デバ)は,その名のとおり裸で出っ歯の齧歯類である(よく見ると感覚毛と呼ばれる毛がまばらに生えており,正確には無毛ではない)(図1).自然下ではアフリカの角(つの)と呼ばれる領域(エチオピア・ケニア・ソマリア)のサバンナの地下に,大きいものでは数kmに及ぶトンネル状の巣を形成して集団で生息している.暗い地下のトンネルに住んでいるため,デバの目はほとんど見えずわずかに光を感じられる程度である.また,野生のトンネル内では低酸素環境(約7% O2)で生活している.実験室では,4~20個程度のアクリルの箱をトンネルで連結させて飼育している(図2).デバたちはこのトンネル内を前向きにも後ろ向きにも同じスピードで走ることができる.