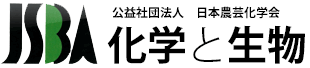Page. 560 - 565
(published date : 2011年8月1日)
一酸化二窒素(N2O, 亜酸化窒素)は強力な温室効果ガスであるとともに,オゾン層破壊の主要な原因物質である.大気中のN2O濃度は,産業革命以前の270 ppbvから,近年にいたるまでほぼ直線的にその濃度が増加し続け,2009年の世界平均濃度は322.5 ppbに増加し (温室効果ガス世界資料センター:WDCGGの解析による),最近の増加率は年間0.26% である(IPCC第4次評価報告書).京都議定書では,CO2, CH4, N2O などの温室効果ガスについて,2008年から2012年の約束期間で,先進国およびロシアなど市場経済移行国全体で約5.2%,日本は6% 削減させると目標値を立てており,地球環境問題の対策として,大気中へのN2O放出量の削減は必要不可欠となっている.