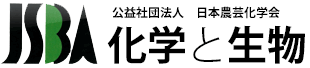Page. 372 - 374
(published date : 2011年6月1日)
ビタミンKは,血液凝固因子の活性化に必要なビタミンとして発見された.その後,血液凝固因子などのビタミンK依存性タンパク質分子の特定のアミノ酸配列中のグルタミン酸残基の γ 位炭素にカルボキシル基を導入する反応(グラ化)を触媒する γ-グルタミルカルボキシラーゼの補因子であることが明らかとなった.グラ化されたタンパク質はカルシウム結合能を獲得し,血液凝固のみならず骨形成や骨折治癒(1),動脈石灰化,細胞増殖・分化など様々な生命反応に関与することが知られている.納豆摂取などのわずかな例外を除くと,通常の食事から供給される主なビタミンKはフィロキノン(ビタミン K1, PK と略称)である.しかし,我々の組織中に最も高濃度で存在するのはメナキノン-4(ビタミン K2, MK-4 と略称)である.この理由は,体内でPKがMK-4に代謝変換されると考えると理解しやすい.最近,筆者らは哺乳類組織内でPKがMK-4へ変換されることを科学的に証明し(2),この反応に関与する新規酵素UBIAD1を同定した(3) ので紹介する.