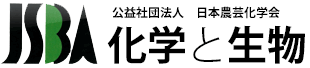Page. 587 - 587
(published date : 2011年9月1日)
2010年11月に日本食品標準成分表が5年ぶりに改訂され,『日本食品標準成分表2010』(以下,食品成分表)が出版された.同時に1986年以来,ほぼ四半世紀ぶりに日本食品アミノ酸成分表も改訂され,『日本食品アミノ酸成分表2010』となった.1955年に掲載項目数14,収載食品数538でスタートした成分表も,項目数50,収載食品数1,878という充実した姿になった.先達の見識と努力に敬意を表するばかりである.